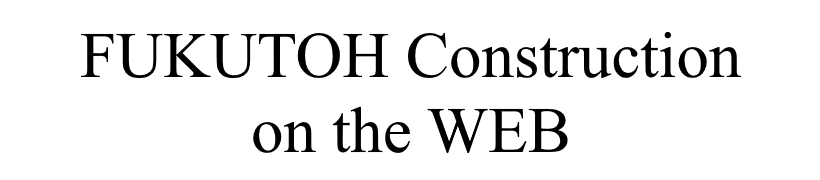以前のブログでもご紹介したNHK Eテレで放送中の「3ヶ月でマスターするアインシュタイン」ですが、だいぶ佳境に入ってきましたw
時間がなかなか合わないのでNHK+で見逃し放送を見ることがほとんどですが、今回の「第11回 世界は「何」でできている?」には、はっ!とさせられました。

物理学、それも量子力学の分野にまで番組は進んできているわけですが、内容も高度になっていく割には、小林先生の説明が非常にわかりやすく、福田さんとの掛け合いも相まって、説明されていることが学問的というより日常目線で理解できることが素晴らしいと思います。第11回では、アインシュタインが目指して敵わなかった「力の統一理論」ですが、この説明そのものが、今、社会でも言われている「多様性」の本質をついていると感じました。
建築も物理学には大きく影響を受けていますが、その建築を学ぶ場合には結局、「見えるもの」、「見えているもの」を対象とします。構造力学にしても、環境計画にしても、意匠にしても、見えるものが対象です。
そして、その「見え方」が、ある一定の法則や、一定の形を成していることを人間は知り、そして、それを解釈するわけですが、重要なのは、知らず知らずのうちに「似たようなことを理解するのに仕分けをしている」ということなのです。
これは思考の方法なのですが、Aという事実や事象があった場合、似たようなA’を経験した場合、Aを元に考えるというのが一般的なわけで、このAという事実や事象そのものは「今見えている様」なわけです。
さて、自然界には「重力」「電磁気力」「弱い力」「強い力」の4つの基本的な力が存在しているのですが、これらを個別の、前述のAやBとして扱っていた力の理論を、統一させるというのが、アインシュタインの目指した「力の統一理論」なわけです。失敗しましたがw
そして番組では「超弦理論」に話しが展開されます。「見え方」の問題の核心部分に突入してきます。「次元」の話しです。我々は3次元の世界にいると言われます。これは目で見たモノがすべて、幅、奥行き、高さで表されることから言われています。
超弦理論を用いて解釈すると、世の中は10次元であることが理論上の条件になるようですが、実際に、見えているのは3次元なわけです。残りの7次元は「見えない」わけです。
これを番組では2つのこと事例で説明していました。
一つは、紙を丸めて棒を作るという例です。紙を細く細く丸めていくと、円柱として3次元であったものが、限りなく細くなることで、棒(線)になることで、1次元になるという説明です。3から1の次元低下があったというわけです。
もう一つは、こちらのほうがよりインパクトが強かったのですが、綱渡りの綱を例に出していました。綱を渡る人は前か後ろにしか行けません。これはある意味、一次元なわけです。でも、この綱に「蟻」がいて、蟻からみると、前後だけではなく、綱の下側まで回り込むことができるわけです。言い換えますと、人から見れば一次元ですが、蟻から見れば3次元なわけです。人間としての「大きさ」があるせいで、今、見えている様が3次元であるだけで、人間が可能な限り小さくなればその次元が変化する可能性があるというわけです。
今見えているモノがすべてではないという発想というのは、まさに多様性を考える上では必要なことですが、それは物理の世界でも、社会問題においても同じ土俵ではないかと感じています。そして、具体的かつ理論的に思考される物理学の世界でもまだまだわかっていない多様性に関する課題が統一されたときに、なんとなく「社会的な多様性問題」も解決されるのでは?と感じました。
ぜひ、一度ご覧ください。