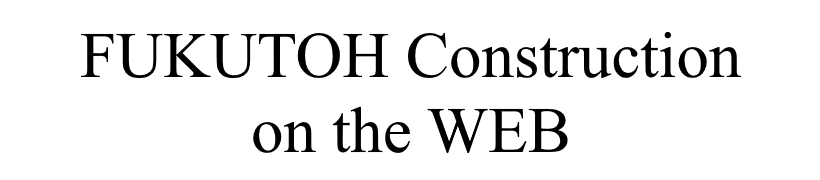児童福祉施設の確認申請審査における「指摘事項」が返ってきました。

未だにFAXなんか!とびっくりされるかもですが、まだまだFAXが現役ですw 民間の審査機関ではほぼメールだとは思いますが、お役所のほうはまだまだFAXなんです。このFAX、「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」と一緒に送られてきますw

これは、法律で確認申請に対して確認審査期間が定められていて、建物の用途、規模によって1号から3号で違いが定められていて、その期間に審査が終わらないなら発行される書類です。まぁ、今回は特殊建築物とはいえ、木造平屋で200㎡以下ですので、いわゆる新3号と言われる部類ですので、原則7日間で審査が終わらないとだめなわけですが、終わらないので発行されますw
ちょっと気になるのは、別で行われている「消防同意」というのがあって、それが終わったという連絡があったら修正した資料を提出してって書いてあるのに、通知書には、提出期限が打たれているので、消防が同意に時間かったらどうなんだろうwって、もやりますw
指摘内容は申請書の記載内容の不備、欠落でしたので大したことはないんで、もう直しちゃいましたが、その指摘の中で「あ?」っていうのがあったのでご紹介しておきますw まぁ、今日のブログテーマである「法律の文言解釈」っていう部分でやられたwって感じです。指摘事項の原文のままを出しますw

これは、建築基準法第28条にある「居室の採光及び換気」に関する規定に関する指摘です。建物には用途や規模によって、居室の採光面積に対して、その室の床面積の一定割合の大きさを求めます。これを「採光計算」とか「採光無窓の検討」と言われています。クリアできない場合には別の手段を講じることで認める場合もありますが、用途によっては「絶対ダメ!」ってのもあります。まぁ、一般的な設計では確実にクリアするようにすることがテッパンですが、なんと、これに対して、
「おまえ、割合がちげぇよ?」
っていう指摘が来たわけですw で、その割合っていうのは、建築基準法施行令第19条から記載があります。規制を受ける「居室」は以下の通りです。
一 保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室
二 診療所の病室
三 児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)
四 児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの
五 病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの
今回の申請は「児童福祉施設」ですので、上記の第四号と第五号のどちらかに該当することになります。

すると、居室の種類と割合の表より、
第四号なら 1/7
第五号なら 1/10
の割合になるってわけです。では、もう一度、その四号と五号をみてみますが、
四 児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの
五 病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの
違いを抜き出して書くと、
4号は、
「入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの」
であり、5号は、
「入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの」
です。この施設は、児童福祉施設ですが、実際の施設業務としては「放課後等デイサービス」にカテゴライズされるものですので、その施設に宿泊することなどはありません。乳幼児は対象としませんし、小学生以上で学校の帰りに立ち寄る、または保護者の送迎で施設までやってきます。また、預かり見守りすることがメインの業務ですので、いわゆる「保育」とも位置づけが違いますし、なんらかの訓練(リハビリ)を行うこともありません。
従って、解釈としては、「第四号」には該当しないので「第五号」という認識でいました。さらに、この児童福祉施設は、福井市内ですでに2事業所が開設、運営されており、もちろん「第五号」として確認申請も済証をいただいていますw
ところが、今回の申請での指摘事項には、
「おまえ、これ、4号じゃね?」
っていうわけですw これは「はぁ?」としか言いようがありませんw それで「なんでやねん!」っていうことを丹南土木事務所に電話して「お聞き」することにしました(あくまでも、はぁ?ではなく、お聞きすることにしたわけですwww)。
でも、その前に、前例がありますので、福井市に対しても問い合わせをしましたw まぁ、今さら問い合わせたって迷惑なだけですが、一応、法解釈としての当時の判断を確認するってことでです。さて、その判断はやっぱり同じ認識で、
保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるものではない児童福祉施設等だから第五号となる。
ってわけです。「デスヨネw」なわけですw
で、丹南土木事務所に電話して、「なんで第4号なんですか?福井市では2棟出してて第5号として認識されてますよ?」と申し上げると、
「それは福井市さんの判断ですよね?」
と前置きされた上で、
「放課後等デイサービスって、子供さんを通わせるんですよね? 通所ってことですよね?入所や入院とは違いますよね?」
といわれ、
「施設に入院したり、入所したりしてそこに居続けるわけじゃないですよね?そもそも、第五号には通う者という文言はありません。第四号には通う者という表現があります。これがこちらの判断根拠です。」
もはや具の根もでませんwww 法律は文言解釈で判断しますが、その解釈はあくまでも「文中表現」に沿って行うものです。要するに、施設の運用実態が保育であろうが、なかろうが、あるいは訓練しようがしまいが、判断の基準は、
「通所しているのか、入院・入所しているのか?」
でしかないとおっしゃるわけです。これにはもはや反論はできませんでした。というのは、法律の解釈としては、済証を発行する権限者の解釈が絶対になるのと、それが「合理的に完全に間違っている」と言えないかぎり抗弁できないからです。まぁ、採光面積の割合ですから、よほどギリギリでなければ、1/10→1/7になっても問題はありませんw
「あ~ なるほど、そういうご判断ですか。わかりました。それでは修正いたします。」
と引き下がることにしました。法的な判断はどれに当てはまるか?という部分で「言葉の解釈」が問題になりますが、まさかの指摘で久々にビックリしましたw