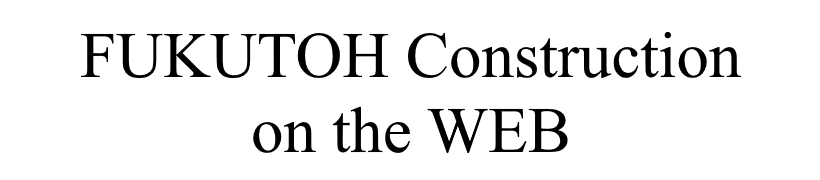「生けどり」というと、なにか狩猟でもして獲物を活かしたまま捕まえるって感じかもですが、建築の作業工程の中には実は「生けどり」というのがありますw しっかり漢字で意味を持たせるのであれば、
「活け採り」
がよいかもしれませんw この「生けどり」といわれる作業を今日、行ってきましたw 築35年を超す木造住宅です。


住宅の一部改造工事なのですが、この吹抜けの大空間に動線を補完するための「キャットウォーク」をつくる計画です。こんな感じの「キャットウォーク」です。まぁ、普通に吹抜けに廊下をつくるったわけですが、ちょっとカッコよく「キャットウォーク」って言ってますw

三次元データも用意してみましたw
既存の吹抜けには、柱・梁やマグサが露わになっている「真壁造り」ですが、ここに梁を追加して一部床をつくるという工事です。
さて、これを新築的な発想で工事を行うのは実は非常に危険です。35年経過している構造体というのは、経年変化でズレやねじれ、傾きなどもありますので、単に柱間を計測して長さを切り出してもうまくいきません。ズレや傾きなども考慮した形での計測が必要になりますが、これを「生けどり」といっています。




「生けどり」のためには、基準となる「軸芯線」などを出す必要があります。コンクリート土間に基礎の立上りの墨を出すような形で、室内に墨を出すわけですが、仕上がりの床に墨を打つわけにはいきませんので、養生した上に軸芯線が通るところに紙を敷き墨を出します。
これが「梁をかける基準線」になるわけですが、この部屋が定規で線を引いたような四角であることはまずありませんw 柱位置が多少ねじれていたりすることで、少し出っ張っていたり、引っ込んでいたりするわけです。基礎などは地べたのことですので、養生の上に敷いた紙の上に絵をかけば終わりですが、梁は「空中に掛ける」わけですので、その出入りを測るのは空中で測ることになりますw

梁が掛かってくる位置の墨を実際に取り付けるところに出していきます。そして、その間などを計測していくわけですが、



微妙な寸法の違いがあるわけです。これらを計測して、実際の梁の切り出し長さを求めないと、既存構造に対してこれだけの追加の構造材を配置することはできません。今日のところはまずは切り出し梁の長さを確実に押さえることが目的です。
この後、まだ生けどりの必要があります。それは、梁が取り付くところの梁や柱の傾きです。

極端な例ですが、赤の線を今の柱や梁面だとすると、それ自体に傾きがあれば、新しく増設する梁の小口もその形状に合わせた「傾斜」が必要になります。単に梁の高さだけ合わせると、下は入るけど上は入らないということが出てくるわけです。
これらの「生けどり」計測の精度が悪いと、せっかく増築した「キャットウォーク」になんだか傾きが生じたり、床鳴りがしたりしますので、かなり神経を使う作業だったりします。
また経過はブログでアップします♪