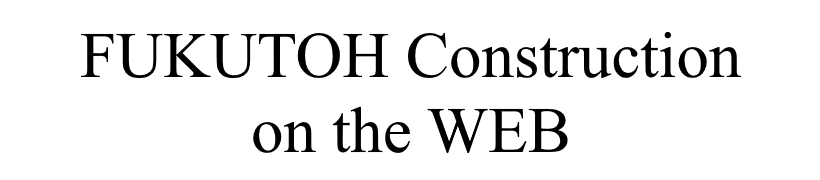まぁ、今さらながらの話題なんですが、BXカネシンさんから、2023年、今から2年ほど前に「BX高耐力たる木ビス」というものが発売されました。
なんで、こんな2年も昔の話題を出してくるのか?といいますと、この「BX高耐力たる木ビス」でかなり設計が楽になるということと、コストダウンも図れるということがわかったからです。まぁ、これも今さらな話しなんですがwww
実は、木造建築での構造計算で「許容応力度設計法」に準拠して設計を行うと必ずぶち当たる「壁」があるのですが、それは「構面力の計算」というものです。構面力には2つモードがありまして、一つは「鉛直構面」、もう一つは「水平構面」というものです。かいつまんで説明しますが、あまり、よい資料がなかったので、「株式会社インテグラル」さんが運営する「ホームズ君.com 学ぼう!ホームズ君」より引用します。
まず「鉛直構面」についてです。ざっくり言いますと、建物の「層(1階、2階、3階など)」に対して、地震時に水平力が加わったとき、耐力壁となる壁でその水平力を受けるわけですが、それぞれ連続的に直線配置される壁に対して水平力が平均的に作用するわけではなく、負担する力の大きさが違いますので、その大きさに対して直線配置された壁が大丈夫なのか?を検討するものです(以下、すさまじくわかりやすい解説図ですw インテグラルさん感謝です!)。

この図を見ていると、「これって筋交い量の計算と何が違うの?」と思われるかもしれませんが、「筋交い量の計算」は、単純に床面積に対し必要な「壁量」を算出して、それに相当する「量」がバランスよく入っていればクリアする話しでしかありません。2025年4月からは「建物重量」について若干考慮するようになりましたが、単に量的ルールであることは否めません。
それに対して、「鉛直構面」を検討するというのは、層ごとに実際の建物重量から導き出される水平力をどこの壁のラインでどの程度引き受けることになるのか?を計算した上で良否を検討するものですので、量ではなくあくまでも力の大きさの問題を考えているわけです。したがって、重量がある建物ほど、この「鉛直構面」は強烈なものを要求されることになります。重量とは「雪」も「風」も含みますので、福井のような多雪地域で「鉛直構面」を検討しないというのは、もはや、力学的根拠を軽視した設計といわざるをえません。
ですが、この「鉛直構面」の安全性を担保するためには、ざっくり言いますと、壁を強くすればいいわけで、例えばシングルだった筋交いをダブルにするなど、比較的対応は簡単なわけです(たまに、アカン話しもありますが、それは間取り関係で無理があるって証拠だったりもしますw)。
さて、「水平構面」についてです。「鉛直構面」が壁だったわけですが、「水平構面」の場合には、各層の上部の水平面の耐力の評価になります。1階であれ2階の床、2階ですと屋根部分という感じです。考え方はほぼ「鉛直構面」のときと同じです。

画像中の難しい式はちょっと置いておいて、右下の図をご覧ください。これまたざっくり言いますと、1階に作用する力と、2階に作用する力がそれぞれ逆方向になるとき、床面が引きちぎられることになるってことで、それに応じた耐力が床面(屋根面)に存在しているのか?っていうことを検討するのが「水平構面」の検討というわけです。
いずれの構面検討も、「面としての耐力」を検討するわけですが、なぜそれを検討しなければならないか?といいますと、
「建物が水平力に抵抗するのは「壁」の役目」
だからです。筋交い単独の役目ではなく、それらが連続的に配置された建物全体の壁で抵抗するわけですので、その壁がもたなかったら地震での倒壊につながるというわけです。筋交い量の計算では、量の計算でしかないというのは、まさにこの点の違いなわけです。
でも、「鉛直構面」の場合、壁をどんどん強くすればOKだったわけですが、事実上それは、壁の量を増やせば済むわけです。ところが「水平構面」の場合は?というと、「床の量を増やす」ことはできませんよね?それやると間取りがどんどん大きくなりますから、当然、重量も増えますので、必要になる構面力は増大していきますw 要するに「水平構面」を検討するには一定の面積の床の量が決まってしまっているので「上限」がある!というわけです。
でも、「床を固くすればいいんじゃね?」って思われるでしょうw それも、一般的な木造の床の作り方では限界があって、方法論としては、
・構造用合板を厚くして(評価24mmまで)、釘をいっぱい打つ(150ピッチ、N75など)
・火打ちを入れて固める
・水平ブレースをいれて固める
くらいしか手がありません。
さて、最近では、2階の床の作り方は、梁の上に構造用合板24mmなどを敷きこんで釘打ちすることで床の構造を作る手法(根太レス工法)というものが一般的です。この工法を採用すると、事実上、2階の床面に火打ち梁をを用いずとも水平構面の剛性を確保できます。非常に都合がよいですw
ところが、屋根面の場合にはそうはいきません。屋根部分は、基本、床がありませんので、水平構面の剛性を確保するためには、屋根を支える小屋組に対して「火打ち」を入れ固めることと、屋根面そのものを固めるしかありません。そうしますと、雪国では積雪重量を見ますので、深度によってはクリアするのが難しくなったりします。弊社ではそれをクリアするために、「水平ブレース」などを多用したり、2階の耐力壁の配置を工夫したりしてなんとか計算上の強度を保ってきましたが、非常に苦労が多かったのです。特に、非住宅で大きな面積の建物の場合はその苦労は甚大です。
もちろん、クリアできないわけではありませんが、その設計の結果、現場施工で多大な負担をかけることになる場合も出てきます。何か改善できないかなということで探していたのですが、すでに、BXカネシンさんでは2年前に解決されていたということがわかりました。
「もう!早く言ってよ!」
な感じですが、それが「BX高耐力たる木ビス」なわけです。


屋根面は、梁や桁に「垂木」という細長い材を配置して、屋根面をつくります。この垂木を留めつけるのは「鉄くぎ」を採用するところは多いですが、「鉄くぎ」では風で煽られたときに屋根全体が抜けて飛ぶということが発生します。もちろん長い釘を使えば防げますが、短い釘で適当に施工したりすると飛びます。また、明確に使用釘の説明がないので、結果として大工さんのもってる釘で留める感じになります。ちなみに100mmの釘ではかなり厳しいです。この場合、あおり止めという金具を軒先に取り付けることで吹き上がりに対応することが求められます。
ですが、最近では省施工と金物省力という部分で垂木を留める「ビス」が多用されていました。ビスですので引抜力への対応もデカく、結果としてあおり止めの金具設置の必要もなくなったわけですが、単に、それだけのことで、屋根面の「構面力強化」という部分では寄与できていなかったわけです(正確には、寄与してたかもしれないけど、実験とかしていなかったというわけです)。
そしてこのビスを「構面力強化」として使う場合の諸元がこんな感じです。

弊社が使う垂木は、45×54~60です。ピッチは303が標準です。それ以上は、積雪荷重に対応することができません。となりますと、このビスで垂木を留めるとなんと、
1.9倍 3.86kN/m(ただし、勾配低減なし)
なのです。一般的な仕様では、以下の表にある通りで、おおむね1倍切っています。よって、ビスを使うことで耐力は2倍以上アップすることが期待できるわけです。

これまで、どうしても高倍率の屋根構面にする場合には、以下のような手法をつかっていたはずです。
・構造用合板を24mm以上にし、屋根面を床の作り方と同じようにする。
・小屋組の梁や桁上に疑似床をつくり24mm構造用合板を張る。
・水平ブレースの多用
まず、コストはどれもアップします。さらに、最初の案の場合には、屋根面の通気をとるためには、通気層を確保するために「二重屋根」にする必要があります。作業も煩雑になります。ところが、このビスを使えば、現状の設計での2倍の耐力があるわけですので、ほぼ、水平構面の耐力検討はクリアできることになります。
あとはビスのお値段ですが、元々、弊社では垂木全数をすべてビス止めしていますので、そこを置き換えるだけです。試算すると、お値段の差として、数千円程度アップするだけwww
これは使わない手はありません。現場施工も非常に楽になります。早く気が付てよかったwww