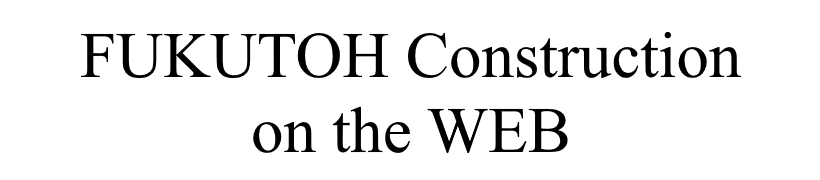前回に続きます。
前回は令46条2項ルートをとる技術的な理由を説明しました。告示1100号別表に記載されない耐力壁の仕様を使う場合は、それ自体の性能が第三者機関での試験結果を元に、大臣認定を取得できれば使えるわけで、その際の使用条件として、令46条2項ルートによる構造評価が必要だという流れがあるわけです。そしてそこには「コスト」をしっかり考える必要があることも書きました。
さて、ここからは個人的な感覚といいますか、考えにはなりますが、構造計画を考える上で重要になるのは「できるだけ一般的な流通材」で設計することです。これは、建物の規模が大きくなればなるほど重要になります。建物が大きくなると設計で扱う荷重が大きなレベルになったりすることで、その荷重に対応するために構造材をかなり強いものを選定する傾向があります。例えば、中国木材さんが扱っているラミナビームのホームページでは以下のような表が公開されています。材料強度ですが、梁材として使われる対称異等級構成材であれば、E135、あるいは、E105、E120が掲載されています。言い換えればこれがラミナビームとしての「一般的な流通材」なわけです。これでもかなりの強度です。

もちろん、これ以上の強度のものをつくれないか?といえば作れます。特注材です。例えばE150を超すような強度の高いものは製作ラインナップあったとしても、それは「受注生産品」ですし、当然、価格も高くなりますし、納期もかかるわけです。
さて、話しを令46条2項ルートに戻します。このルートの最大の目的はなにか?といいますと、
大空間の設計や、大きな吹抜け、また、大開口の設計を行う際に、どうしても不利になる「壁量計算」、「壁のバランス(特に四分割法)」の適用を除外する。
ことにあります。ただし、その時の条件は「構造計算を行う」ということになりますが、構造計算を行えば「壁量計算」、「壁のバランス」の検討が必要ないわけではありません。構造計算を行う場合でもこれらの検討は必要なのです。あくまでも、令46条2項ルートを使うことによって、使用材料を規制した上で、構造計算によって安全性を確認できるなら、その過程での「壁量計算」、「壁のバランス」の検討はしなくてもいいというだけのことです。さらに「構造計算を行う」ことだけに注目すれば、その計算のために「無等級材」を使ってはいけない、無等級材では構造計算ができないなどということは、まったくないのです。
単に構造評価のステップを一つ省略したいだけのために、わざわざ令46条2項ルートをとり、かけなくてもよいコストをかけるような設計手法をとるところが増えているというのが個人的な感覚です。建物の意匠上の問題により、どうしても令46条をクリアすることが難しいから適用除外をするために、構造計算をした上で材料規制を受けるというわけではないのです。
さて、ここで、2025年4月から運用される建築基準法上の構造関係規定の評価フローを示します。

実はこの度の改正で、令46条2項ルート以外にも、「壁量計算」、「壁のバランスの検討」に関する適用除外ができました。それが、「告示1100号第5ルート」というものです。
次回はこの「告示1100号第5ルート」を掘り下げます。