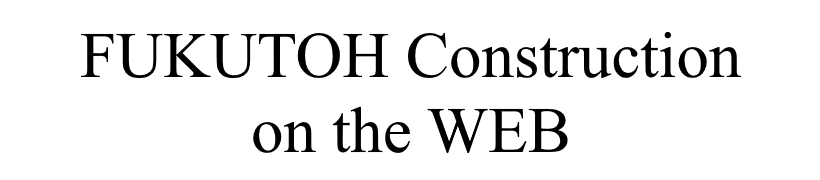前回に続きます。
さて、2025年4月から施行されている改正基準法では、告示などの改正も行われています。その中でも木造に関する極めて重要な改正が、
「告示1100号 木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件」
の改正です。その中でも「第5」はかなり注目される改訂です(新規追加です)。以下、条文です。
昭和56年建設省告示第1100号
木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件
第5
令第88条第1項に規定する地震力により建築物の各階の張り間方向又は桁行方向に生ずる水平力に対する当該階の壁又は筋かいが負担する水平力の比が0.8以上であつて,かつ,昭和62年建設省告示第1899号に規定する構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた木造の建築物(地階を除く階数が3以下であるものに限り,直交集成板を用いたパネルを水平力及び鉛直力を負担する壁として設ける工法によるもの及び短期に生ずる力に対する許容せん断耐力が1メートルにつき13.72キロニュートンを超える軸組を用いるものを除く。)にあつては,第2から第4までに定める基準によらないことができる。
この第1100号では、具体的に筋交いなどの耐力壁といわれるものの仕様が定められています。今回の改正で追加された壁仕様もたくさんあり、高倍率の強固な壁仕様が認められています。また、当然、これらを組み合わせることでより高倍率の壁を構成することができます。これら告示に記載されている壁仕様のことを「告示壁」といわれることがあります。告示壁はすでに実験などによる検証を経ており、特殊な仕様の壁ではなく国が用意した耐力壁仕様であると位置づけることができます。したがって、「告示壁」を使うことで設計評価はかなり楽になります。木製の筋交いなどは以前からこの「告示壁」に含まれている壁仕様です。
その第1100号では、第2から第4までで、
・耐力壁の仕様
・必要な壁量の規定
・壁のバランスの確認
といったことが規定されています。施行令46条をクリアするというのは、この告示1100号の規定をクリアすることと同義です。その項目の中に、第5として先ほどの条文が組み込まれました。
第5では、ある「一定の基準」をクリアするのであれば、第2から第4までに規定で縛ることはないというものです。その「一定の基準」とは、
・水平力(地震力)に関する抵抗を80%以上「耐力壁」で受け持つ
・耐力壁の倍率は7倍以下(超えることはゆるされない)
・CLTの利用は不可
・構造計算を行い安全性を確認すること
というわけです。ここで、木造の構造安全性の評価のフロチャートの一部を示します。

前回のブログでもご紹介したフロチャートですが、令46条2項ルートというのが、このフロチャートでは「集成材等建築」と記載されているところです。無等級材を除く構造用製材と構造用集成材を使うのであれば、この「集成材等建築」と書かれているところでYesに進むわけです。ところが使用する材料に制限があるわけですので、県産材に代表される「地域材」といわれるもので、一般の製材所が加工する木材をそのまま使うということができません。JAS認定工場から出荷させ、かつ、目視等級材、機械等級材として「認証」される必要がでてくるわけです。前回までのブログではこれが結果としてコストを押し上げる結果になるということを申し上げました。
繰り返しになりますが、壁量計算や壁のバランス計算は、木造建築で大空間、大開口の設計を行う際に不利になる「だけ」です。こういった建物は施設系に多いわけで、一般の住宅や小部屋で仕切られる店舗、事務所ではそうあるものではありません。要するに計画する建物自体がある意味特殊なわけです。
特殊な建物である以上、それを定型化された壁量やバランスでの安全性の確認などが当てはまるか?といえばそうでないことの方が多いです。当てはまったとしてもそれは量的なクリアができているだけで物理的な挙動まで追いかけて評価しているわけではないのです。まして面積が大きくなればなるほどその影響は大きくなっていきます。
言い換えますと、その種の建物の構造安全性の評価は「構造計算によって行う」しかないはずなのです。したがって「構造計算するのであれば」は「構造計算するでしょうから」に変わるわけで、材料を何を使おうがそれで制限されるような話しではないはずなのです。地域材といわれる無等級材には、無等級材としての一定の品質を確認できれば強度設定はなされていますし、その最低限の品質というのは、現在の製材加工会社が出すレベルよりもかなり低いもので、ある意味、昭和の一桁の製材品質でしかありません。つまり、JAS認定工場でなくとも、相応の品質と強度を持つ木材を出荷することはできますから、我々設計者は「それに合わせて設計する」だけのことなのです。
その部分を今回の改正では、明確に告示1100号第5にて打ち出していると感じています。
構造計算を行えば、令46条規定の壁量やバランスの確認はしなくとも、構面力として安全性と、壁の存在に対するバランス(偏心率)、さらに、層ごとの変位変形量も計算します。46条の規定を含んだより高度な検討をしているわけです。さらにそれらは想定する荷重を元に計算しますので、雪深いところでは雪を、風が強いところでは風を、そして建物の中に配置するモノの荷重も含めきっちりと想定した計算をします。さらに、その荷重や地震力に対して、柱、梁、基礎といった部位の強度の計算も行います。
安全性を確認するという意味合いでは、すべての内容をつぶさに確認するわけですので、それが、集成材でなければならないとか、JAS認定工場から出荷されたものでなければならないという理由など構造計算上はどこにもありません。
地域材としての無等級材を、単に法律の一解釈として緩和規定にのってこないことを理由に否定する設計は設計ではないと断言しておきます。