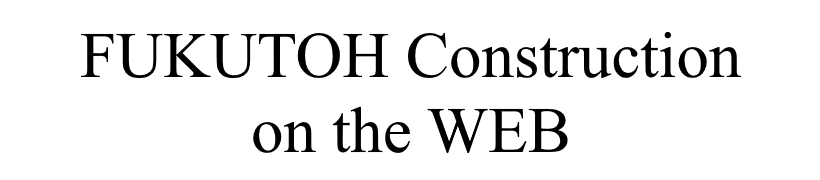#1に続きます。
問題にしたいのは、この「四分割法」による耐力壁のバランス確認が、法的な「仕様規定」に含まれていることで、その手法については、
- 床面積を4分割する(面積ではなく縦、横に4等分)
- 4分割の両端部分に対して、面積と係数から算出される必要量が存在しているかを判断
- 存在量<必要量となる場合には、両端部分で小/大の存在量の比が0.5以上かどうか?
この3つの要素をクリアすること以外書かれていません。どんな平面形状の建物でも、この3つの評価さえクリアできれば「耐力壁のバランスは法的に問題ない」というわけです。では、以下のような建物の場合はどうでしょうか?

非常に大きな家ですが、こんな家は福井ではどこでも見かけるようなレベルの住宅です。田舎ですのでw
赤と青のラインは、それぞれの方向で4分割した場合の1/4のラインを表しています。法律を解釈してそのまま1/4とした場合には、このような分割になるわけですが、これで各々の両端に存在している耐力壁の量を法律で定められた手順で評価しクリアしたらバランスがよいと言い切れますでしょうか?
この建物は形状か見ると3つの部分の「塊」で構成されています。

少し話しは逸れますが、構造的な分離(エキスパンションジョイントといいます。以下、EXP.J)など昔の建物ではなされているようでなされていません。EXP.Jとは完全に切り離された構造で、ちょっとした仕上げ材で見た目がつながっているように見れるだけで、地震などで力が作用した場合には、その仕上げ箇所でわざとちぎれてしまうように作ることで、個々の建物がもつ固有の揺れの状況を保ち、建物全体の損傷レベルを抑える効果を望むものです。ですが、昔の建物の場合、仮に柱などを2重にして設置されていても、相互に釘留めされていたり、あるいは柱は二重になっていても、梁はつなげてあるというような造りになっているために、理想的なEXP.Jの状況ではほとんどありません。
これは古い家を事例としてあげましたが、現在でもここまで大きな変則的な形状でなくとも、L型であったり、出入りの激しい平面形状である建物は当たり前に存在していますし、これから新築しようと希望する方の間取りの構成、敷地の状況への対応となれば、建物がマニュアルのような整形になることばかりではありません。
離れ的に奥まったところに夫婦の寝室を計画し、その部分だけが全体から突出していたり、2階がツインタワーのように2つの塔状になっていたり、その場合でも、この「四分割法」によるバランス確認がそのまま使えるか?といいますとかなり疑問なわけです。ところが、法が求める仕様規定では平面形状に特段の断りや規制がありません。無いということは感覚的におかしいと感じても、あるいは工学的に判断しても無理だろうと考えられても、この手法をとることを否定することは「法解釈上」できないわけです。
となれば、それは設計者がしっかりと工学的な判断をして、どのように対応するか?と考えなければいけませんが、旧4号特例がなくなりそれで慌てているような設計者にそんな能力は皆無なのです。となれば、法的な手順をなぞるだけですので、このような不整形の平面プランでも四分割法でバランス検討することになりますし、むしろそれを疑問視することもないわけです。
そして確認審査機関ですが、彼らの仕事は法的な審査を行う「だけ」ですので、工学的な良し悪しを個別の事案として指摘するようなことは「ほぼ」ありません。なぜなら確認審査は法やその他のルール上決められた内容に即しているか?を判断するだけで、それ以上のことではないからです。審査官が「これまずくないですか?」と指摘した場合には、その「法的根拠」を挙げて指摘する必要があるからです。
例えばこのような不整形で、赤と青の線で分割されているものを見て、「これはおかしい」と感じたとしても、法的な根拠条文、あるいは運用規定ルール、所管から出されている通達等、どれかに該当していない限り「法に不適合である」という指摘はできないわけです。そして、この四分割法については法の仕様規定にそのまま記載があり、特段、不整形の場合の対処方法の規定などないのです。
ここで必要になるのは「設計上の配慮」というものです。不整形であるがゆえにそのまま法的なルールを適用してしまう危険性がある場合、「耐力壁の配置バランス確認」を他の手法で行うことができます。これを「偏心率の計算による詳細検討方法」といいます。
次回はこの「偏心率」というものを取り上げます。