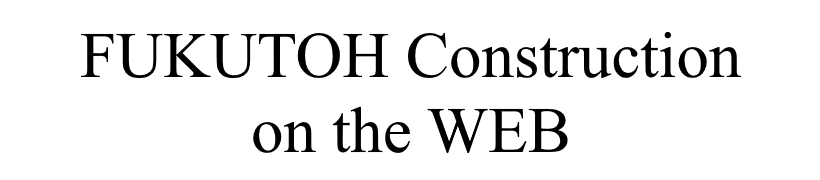福井県では、県産材を使った施設建設に対して「補助金」を出しています。また、建物の建築だけではなく、施設内で使用するための「家具」、「遊具」、「玩具」に対しても補助を出しています。
店舗、事務所、工場、倉庫などを木造で新築する場合にはかなり有効な補助金で、弊社では積極的に利用しています。さらにこの補助金、木造化する場合、建物が300㎡を超せば「設計費用」に対しても補助が出るのです。
300㎡を超す木造建築物には「構造計算」が必要になります。中大規模建築物とカテゴライズされるのですが、木造の構造計算については専門性が高いということもあり、設計費用にも補助が出るという形です。
補助金を出す「助成区分」は以下の通りです。

どのくらいの補助がでるか?といいますと、以下の通りですが、意外と高額の補助金が出されますw

木造化支援に絞ってお話しますが、施設の新築などで、50㎡以上、300㎡未満でも200万円の補助金が出されます。さらに、この補助金の対象は、県産材に対するだけではなく、その施工費(ただし県産材を使う部分に対する施工に限る)に対しても補助対象なのです。補助率は1/3ですので、満額の200万円の補助金を得るためには、600万円の県産材経費が必要となります。これ意外とハードルが低いわけですw 以下はホームページに記載されている「助成対象経費」なのですが、

施工費に関する経費計算では、具体的な経費抽出というのは難しいですよね?大工さんが仕事をするのに、この仕事は県産材に対するものだ、とか、これはちがうというのを具体的に判断することはほとんど不可能です。なので要項では「県産材使用割合」で施工費を按分することを認めています。言い換えますと、県産材の使用割合を増やせば増やすほど、施工費を対象とできる金額も増加するわけです。
近々、建方を行う「児童福祉施設」では、以下のような割合の木材利用率です。
県産材構造材 18.466㎥
県産材非構造材 2.447㎥
国産材 3.133㎥
外材 0.446㎥
合計 24.492㎥
です。この場合、県産材の利用割合は、
(18.466+2.447)÷ 24.492 = 85.3%
となります。つまり、施工費に対して85%も補助対象として見なすことができるわけで、120㎡程度の小さな施設物件でも、県産材費+施工費で600万を超すことは普通にでてくるわけですw
ただし、県産材のメインとなる樹種は「杉」ですので、スパンを飛ばすような設計をする場合には、それなりの工夫が必要です。その工夫は構造計算を行うことで安全性の確認を担保することになります。まぁ、設計をするのに安全性を確認しないような設計で完結するということのほうがおかしいわけですので、できない・していないほうが問題なわけです。
というわけで、施設建築での県産材活用というのは、県の助成制度もあるわけですので、それを活用することで設備投資の経費の負担減につながるように設計施工することは重要なのです。