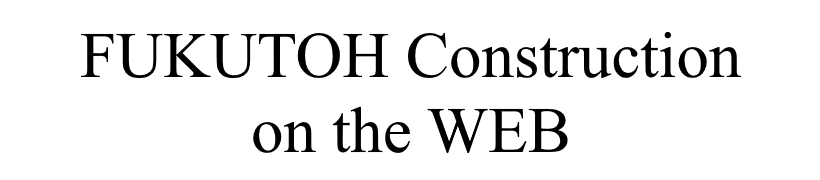木造の建物では玄関先のポーチ屋根を支える柱が「独立柱」とすることを意匠的にも採用することがあります。昔の住宅などでも「土縁」という縁側の外に屋根を突き出して日陰をつくるような工夫をします。

このような独立柱は屋根荷重を支えるだけの働きなので、耐震性を担保するような柱ではありません。ですが、基礎があって土台があるようなところに建てられる柱を違い、位置や高さは結構吟味した計測をしないと、「ここ!」っていうところがなかなか決まりません。
ある程度の位置については、寸法を測ることで決めることはできますが、それが垂直かつ高さが一定で建てることができるか?というと結構厳しいわけです。
例えば木造の柱の垂直精度については「下げ降り」というものをつかって計測します。木造の場合にはそのための専用の道具もあります。
◎シンワ測定 風防下げ振り ベーシック マグネット突き当て

これを2方向から測定すれば、その柱が垂直に建っていることを確認できます。ズレがあれば「屋起こし」という道具で傾きを補正していきます。
◎ナカヤ 鉛直度矯正機 屋起こしナンバーワン極 コンパクト型 NK-4000KWCS 最長400cm

このような道具で施工精度を上げることができるのは、土台や基礎があってしっかり「通り」が出ているということと、土台や基礎の「天端」があるからで、その上に載る柱の高さは自動的に合うのと、土台に空いているホゾ穴があれば、もう絶対位置は合うわけです。
ところが独立柱では、「独立」というようにその位置は「フリー」なことが多いです。先に金物を固定して位置と高さ決めをするようなものもありますが、ちょっと意匠的に採用したくないなぁと思うときは使えません。

となりますと、土縁に使われるような束石のようなもので支える柱が必要になるわけですが、これを建てる場合には結構通りと高さを吟味する必要があるわけです。


基準線を「土台に固定された柱」から300mm程度で出し、その基準線の通りから柱の離れを測定して柱の位置を見ます。柱の根元部分と梁との接合部分で300mmの離れの位置を出し、トランシットを基準線上に設置すれば、柱からの離れの300mmがトランシットでしっかり合えば「柱の通り」は正確であることがわかります。また垂直についてはトランシットの縦の線が柱の角でピッタリ合えば、建入れOKとなります。
高さの方ですが、こちらは基準になる水平を「土台に固定された柱」に出します。この水平は「オートレベル」で覗いたところなので適当な位置です。その適当な位置の線が梁の天端からどれだけ下がっているか?を計測します。今回、1432mmでしたので、独立柱にも梁天端から1432mmを出します。その独立柱につけた1432mmの水平線がオートレベルで覗いたときに合致するところまで柱の下端の高さを調整するというものです。
これ大工さんでは器械を使えないので、管理者の仕事になりますwww 結構、久々にやった仕事でしたwww